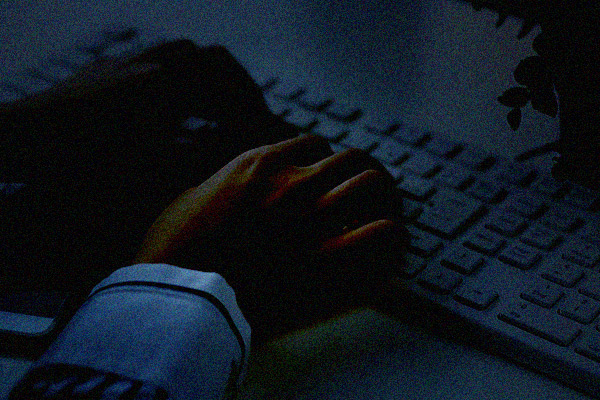
「それでは次回作は、それでお願いします」
編集部の受付前の打ち合わせブースで佳奈は怪談連載しているライターさんに頭を下げた。
エレベータまで見送って振り返ると、直ぐ傍に雪原さんがいてびくっとなる。
「手、怪我してましたよね」
打ち合わせをメモるライターさんの右手には白々とした包帯が巻いてあったのだ。
「……まさか、あれって実話ですか?」
確かに連載されてる怪談の中に傷の話はある。
「違うんじゃない? たまたま怪我したからネタにしただけで。本人も何も言ってなかったし……」
あえて聞きもしなかった。
それから編集部内で右手を怪我する人が続出する。
小指を骨折したり、爪がはがれたり、切り傷、擦り傷、ねんざ……。
「いたっ」
佳奈はシャープペンシルの芯が掌に刺さってしまった。
直ぐに抜くも、黒いのが内側に残っていてすっきりしない。
けれど、どこかほっとしていた。
九州場所が終わる頃には編集部のほぼ全員が手に怪我をしたことになる。
小さいのから大きいのまで、さまざまだが、これで自分の番は過ぎたと思ったのだ。
この程度で済んで良かったと……。
傷はひとめぐりしたような気がしていた。
そして一巡すれば、この呪いのような残穢(ざんえ)も立ち消えるだろうと。
取材先から戻って編集部に入ると、雪原さんが手のひらをこすっていた。
「落ちない、落ちない、落ちない」
鬼気迫る感じでぶつぶつ言ってるから、声をかける。
「どうしたの?」
近づいて手元を覗き込むと、別にどうともなっていないように見えた。
こすりすぎて赤くなってるくらいだ。
「青いマジックが落ちないんです」
なのに、雪原さんは泣きそうな声をあげる。
「別に何もついてないけど」
「そんなことありません。ここに」
と指さされて、ハッと気づいた。
雪原さんは血管の青い筋を落とそうとしているのだ。
それと同時に編集部でただひとり、雪原さんの右手だけがまだ無傷だったと佳奈は思い出す。
翌日から雪原さんには休みを取ってもらい、そのままインターンは終了となった。
ただ間に合わなかったようで、雪原さんは自分で自分の右手の爪を全部剥いでしまったそうだ。
そこまでしても、彼女は災厄を避けられたと安心して微笑んでいたと言う。
雪原さんが来なくなって三日も経った頃――。
「いたっ」
デザイナーの天野さんが仕事中に声をあげた。
一瞬、ざわめいていた編集部の音が止まる。
天野さんは親指を口元に運んで、ぷくりと玉になった血を、ちゅっと吸っていた。
どうやら安全ピンで刺したらしい。
恐らく誰の頭の中にも同じ不安がよぎったはずだ。
二巡目が始まったと。








