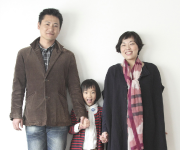青木 耕生(あおきこうせい)さん
『硝子工房 生』代表 ガラス作家
1975年、久留米市出身。九州産業大学芸術学部卒業。『マルティグラス』『萩ガラス工房』での勤務を経て、2005年、福岡市早良区に『ガラス工房 生(せい)』をOPEN。自身が考案した雪花ガラスの創作活動や展示会を行う一方、工房で雪花ガラス体験も行っている。新しく創作した器でお酒を飲むのが楽しみの一つ。
青木さんへ3つの質問
Q. この仕事に向いている人は?
A. 上手くいかないことや苦労も多いから、「ガラスが好き!」なことは大前提だと思います。
Q. あなたのバイブルは?
A. 本というより、人でしょうか。人に習い、助けられ、導かれてきたように思います。
Q. あなたのメンターは?
A. ガラス作りのイロハを教えてくれた師匠・桐島隆氏。引退されていますが、今でも私の目標です。
ガラス工芸は、化学×芸術の結集。
ガラスの持つ可能性を追求していきたい。
奥深いガラスの世界に魅せられて
「小さい頃から、ガラスのとろっとした感触や透明感が好きで、川でよく破片を集めていました」。そう語るのは、ガラス作家の青木耕生さん。ガラス界ではタブーとされてきたヒビを、模様としてあえて取り入れ、「雪花ガラス」という独自のガラスを考案した若手作家だ。『萩ガラス工房』に勤務していた際、「内ひび貫入ガラス」という技法に出合い、理屈だけでは作れない難しさと同じ模様が一つと出ない奥深さに惹かれた。それから五年余りをその制作と研究
に費やし、独自の工夫とアイデアを取り入れたオリジナルガラスをつくるため、工房の設立を決意した。
試行錯誤の末に生まれた「雪花ガラス」
思い描いてきたガラスを形にするには、それを実現するための環境が必要。というのも、ガラスは10種類以上の薬品の粉を「調合」することで、強化・耐熱・フロート…と様々な種類が作られる。その調合のバランスは工房・会社によって違い、それぞれに秘伝の「調合表」があるほどだ。また、ガラスが溶ける温度によって窯のつくりも異なる。そのため、工房ができて初めて、自分の思い描いたガラスの試作が叶うという。「最初のガラス作りがぶっつけ本番
で、もう後には戻れない。想定していた通りのモノが出来上がるか不安で眠れませんでした」と当時を振り返る。
溶解炉で溶けた硬質のガラス原料を巻き取り、軟質ガラスの粉をまぶして空気を吹き込む。そして、再び溶解炉で硬質ガラスをかけて三層構造にし、一晩かけて冷却。室温に戻したとき、その瞬間は訪れる。「キンッ」と音をたて、中間層の軟質ガラス部分に繊細な亀裂が生じた。「本当にホッとしました。雪の結晶のような模様が、ぱっと花開くように浮かび上がるのを見て、『雪花ガラス』と名づけました」。
ガラスの可能性を追求し続けたい
耐熱ガラスのため熱湯も使え、緑茶などの淡い色あいのものを入れると、ヒビの文様がよく映える「雪花ガラス」。『JR九州』のクルーズトレイン「ななつ星 in 九州」の茶器として採用されたのをはじめ、百貨店オリジナル商品の依頼や結婚式の引き出物、両親へのプレゼントとしてオーダーする人も増えている。
「一つひとつ思いを込めて作っているから、『雪花ガラス』を知って、日常の中で使ってもらえるのはうれしい。好奇心を忘れず、新しいものを生み出していきたいですね」。理屈どおりにいかないから工夫し甲斐があり、繊細な変化を生み出すこともできる。困難さえも楽しみに変えて、青木さんはこれからも、ガラスの可能性を追求し続ける。