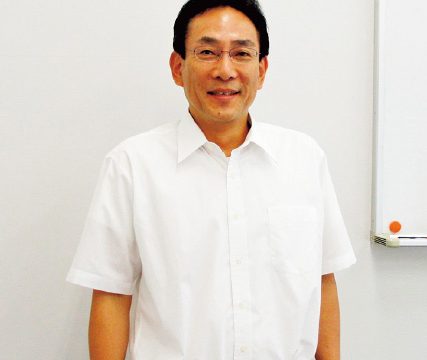妹尾 武治(せのお たけはる)先生
妹尾 武治(せのお たけはる)先生
九州大学大学院 芸術工学研究院 准教授
東京都出身。東京大学大学院人文社会系研究科を修了。心理学博士。専門は知覚心理学で、心理学全般の授業を受け持っている。現在、「ベクション」と呼ばれる、自分が乗っている電車が止まっているのにもかかわらず、反対方向の電車が動き出すと自分も動いているように感じる現象を研究テーマとしている。また、5歳になる娘を愛する1児の父でもある。趣味はプロレス鑑賞。
実は脳は面倒くさがり屋!?
迷信を信じてしまう私たちの脳のメカニズム。
「急いでいるときほど反対車線のタクシーが来る」、「養子をもらった夫婦は、そのあと妊娠しやすい」。これらはいわゆる「迷信」と呼ばれているもの。どうして人は迷信を信じてしまうのか。今回は、九州大学で心理学の教鞭をとる妹尾先生を訪ねた。
人はいいことだけを信じる生き物
迷信だとわかっていても、「ありそう」だと思ってしまう。それはどうしてなのかと、妹尾先生に尋ねると「たとえば、物事の調子がよいとき『波に乗る』と言いますよね。このことをバスケットボール界では特に『シュートが成功すると、次のシュートも成功する』ということを意味していて、昔から信じられているそうです。しかし、これを実際に行われた試合で集計した結果、シュートの成功や失敗にかかわらず、ほぼ同じ確率で次のシュートが決まるということがわかりました。つまり前のシュートは次のシュートの成功には関係がなく、『波に乗る』という現象は起こっていないということがわかりました。いわゆる迷信だったというわけです」と答えてくれた。「人は肯定的なデータにしか目が行かないようになっているんです。自分にとって不都合なことはすぐ忘れてしまいます」。なるほど確かに、人から痩せたねと言われると、本当に痩せたような気持ちになる。このように、入ってきた情報から勝手に推測して、事実とは異なる誤った認識をしてしまうことを「誤信」と呼ぶ。迷信を信じてしまうのも、この「誤信」から起こるものなのだそう。
脳はサボり魔
「友人から、かっこいいという人の噂を聞いて、実際に会ってみるとあまりかっこよくなかったという経験があると思います。これはたくさんの情報を覚えておくのが面倒だから、必要そうな情報だけをかいつまんで、『かっこいい』という部分を強調して思い込んでしまうのです。これは『確証バイアス』という、先入観により解釈してしまうという人の特性です。脳は入ってくる情報をできるだけ最小限にしておきたいんですね」。
その一方で、人はどんな情報でもたくさん集めたがるものだとも先生は話す。「これは、より多くの情報を集めることで、起こるかもしれない危険から身を守りたいという本能が働くと言われています」。私たちの脳は、私たち自身をだますことで身を守っているのだ。
「私たちを本能で守っていくれている脳ですが、実は脳は理論的に思考していません。入ってきた情報を最小限にとどめたりするなど、基本的に面倒くさがりなんです。しかし、一時期『脳トレ』としてはやった、計算や瞬間記憶などの訓練をすることで、その訓練に順応していき、脳の活動領域は広がっていきます。もちろん、その訓練に順応するというだけなので、頭がよくなるとは限りませんが」と妹尾先生。
今回のゼミでは、実際にどんなふうに脳が自分をだましているのかを体験できる簡単なゲームを交えながら、誤信のおこるメカニズムやその原因について学ぶ。
妹尾先生の講義を聞いて、実は脳が自分で自分をだましていることに気づけるかもしれない。